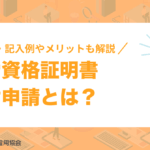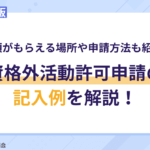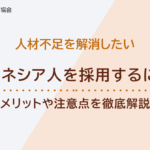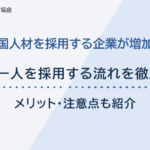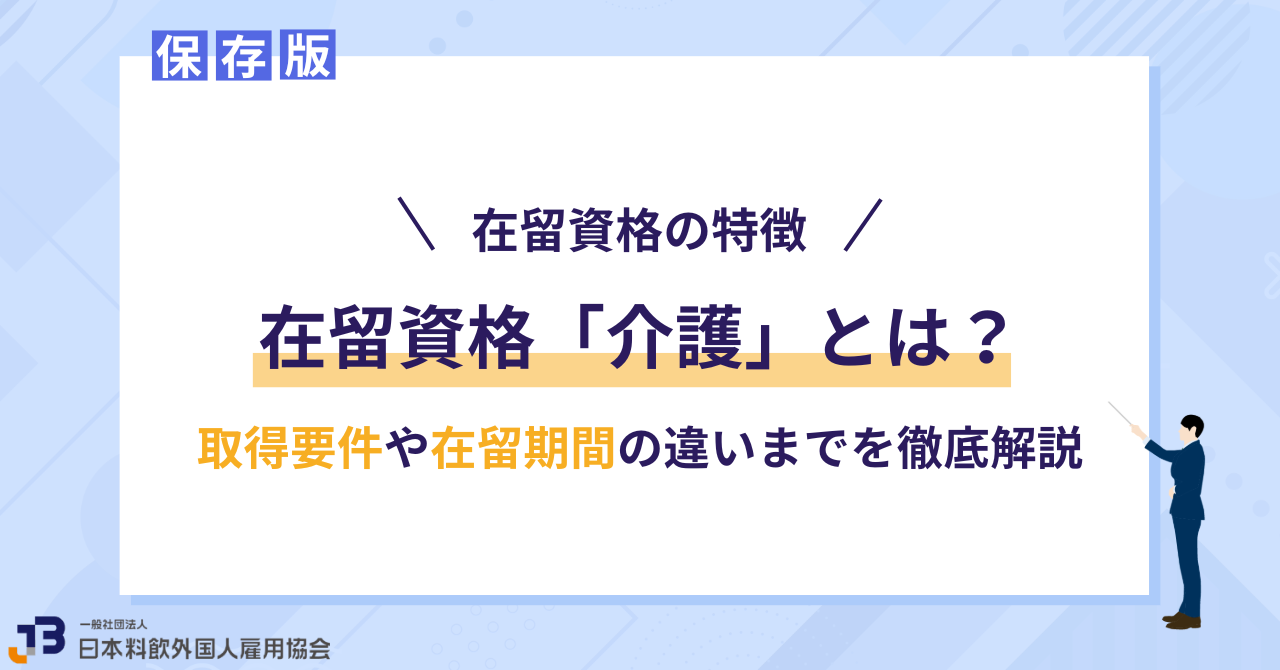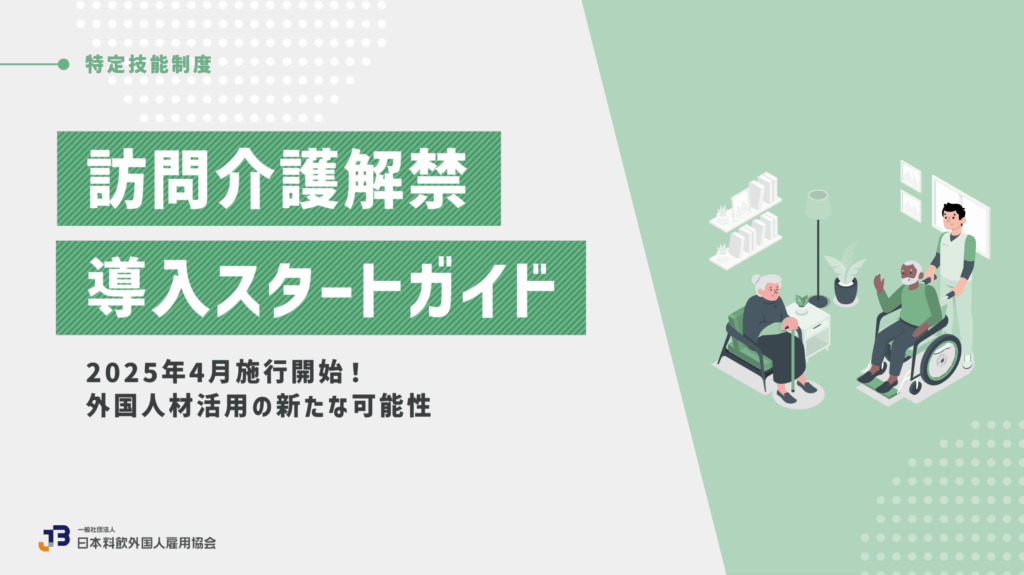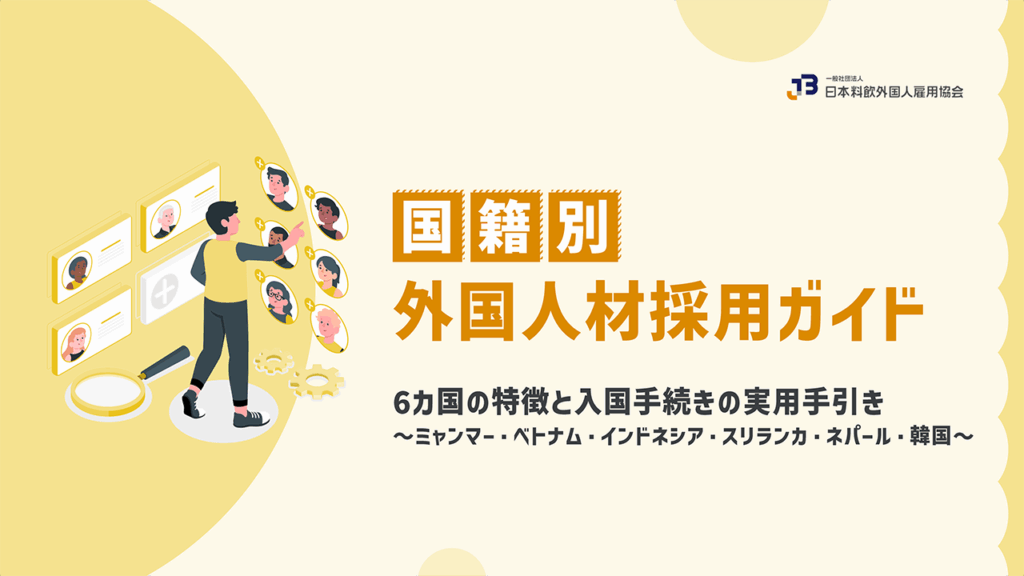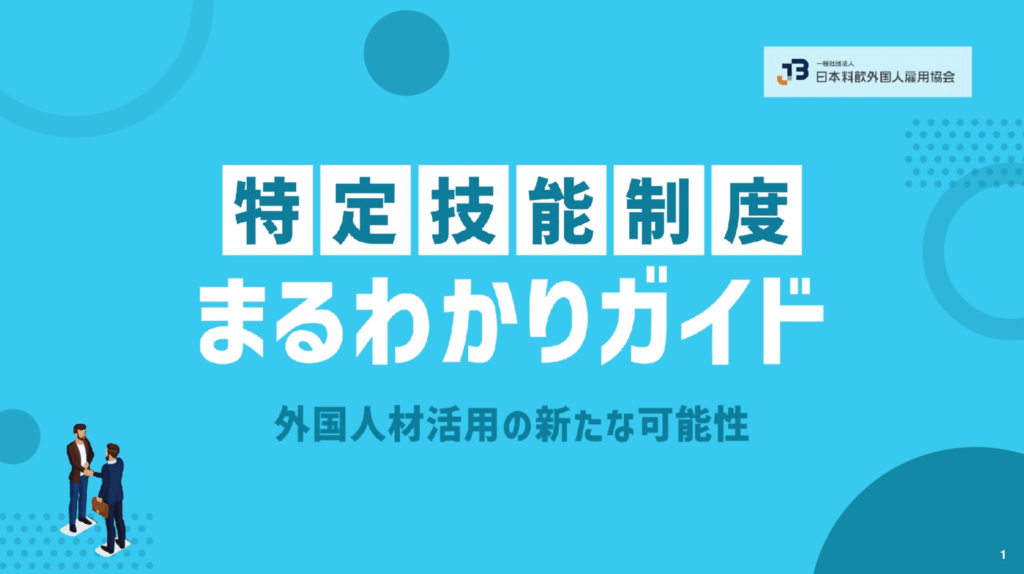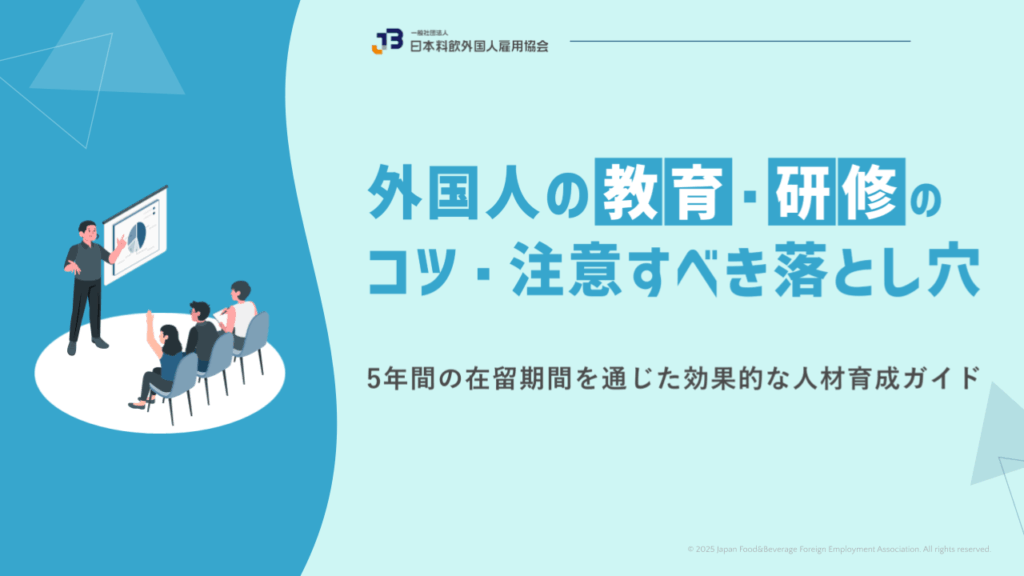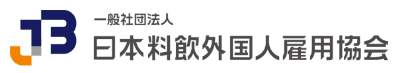「介護の在留資格はいくつかあるけど、それぞれの違いは?」
「外国人を採用するにしても、どの在留資格をもつ人を採用すれば良い?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
介護業界の深刻な人材不足に対応するため、多くの施設で外国人材の採用が進んでいます。しかし、自社の現場には、どの在留資格をもつ外国人を採用すべきかわからず悩む方は少なくありません。
そこで本記事では、介護職で働く外国人が利用できる主な在留資格「介護」「技能実習」「特定技能」「特定活動(EPA)」について、それぞれの特徴や取得要件、在留可能年数などを解説します。
違いを理解したうえで、自社にあった在留資格をもつ外国人の採用を検討していきましょう。
介護分野で働ける在留資格4種
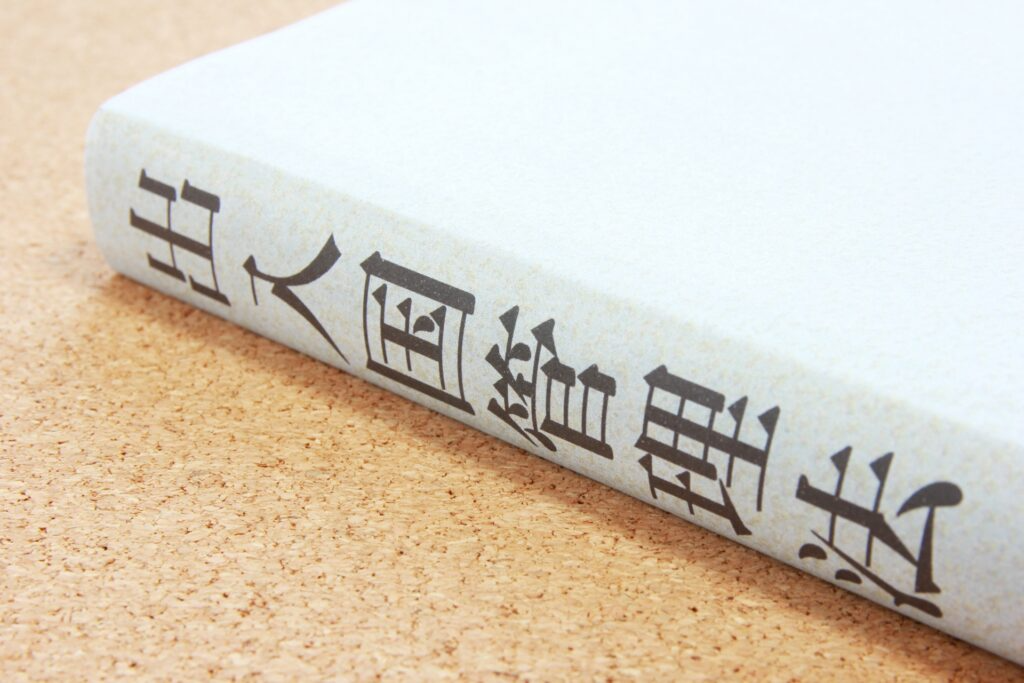
外国人が日本で介護職員として働ける在留資格は、身分系の就労制限のない在留資格を除き、以下の4つが主なものになります。
- 在留資格「介護」
- 技能実習
- 特定技能
- 特定活動「EPA介護福祉士・候補者」
資格ごとの特徴を順番に見ていきましょう。
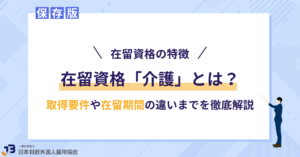
在留資格「介護」
在留資格「介護」は2017年9月に新設され、外国人が正式に日本国内で介護職として就労できる在留資格として位置づけられています。
令和2年4月1日には在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートを問わず、在留資格「介護」が認められるようになりました。
 FES監修者
FES監修者ほかの在留資格とは異なり、日本の介護福祉士国家試験の合格が大前提です。
さらに、合格にあたっては高い日本語能力と専門知識が求められます。
在留資格「介護」による在留期間は3ヵ月、1年、3年、5年のいずれかが付与され、更新回数の上限はありません。職場の雇用契約が継続されていれば長期にわたって在留可能です。
介護福祉士の資格を有するため、老人ホームだけでなく、訪問介護やデイサービスなど、さまざまな介護サービスで即戦力として働けます。
技能実習
技能実習は、外国人技能実習生が介護現場で学びながら実際に働ける在留資格です。
技能実習で在留できる期間は最長5年となっており、契約終了後は基本的に帰国しなければなりません。
これまで技能実習で従事できるのは特定の施設内業務が中心でしたが、2025年4月より運用方針が改正され訪問介護業務へ従事することも可能になりました。
ただし、技能実習制度は今後廃止され、新しい育成就労制度へ2027年までに完全移行される予定です。詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
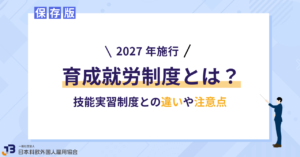
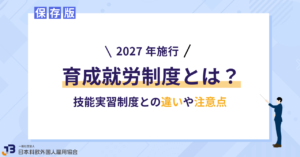
「訪問介護に従事する外国人材の要件を詳しく知りたい!」という方に向けて、特定技能制度 訪問介護解禁 導入スタートガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
特定技能
特定技能は、人手不足が深刻な業界で即戦力となる外国人を受け入れるために作られた在留資格です。
介護分野で特定技能を取得して日本で働くには、介護技能評価試験と介護日本語評価試験、そして日本語能力試験の合格が求められます。
特定技能による在留期間は通算で5年間までです。1年を超えない範囲で指定された期限ごとに更新できますが、5年以上は延長できません。
ただし、在留中に介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格を特定技能から「介護」に変更できます。
変更後は在留期間に上限がない状態で、長期的に日本で就労可能です。
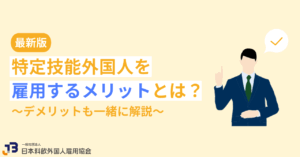
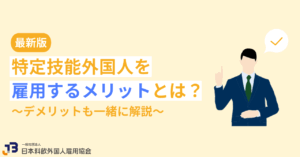
技能実習と特定技能は混在しやすい在留資格ですが、それぞれ異なる点は多いです。以下では、技能実習と特定技能の違いを紹介しているため、参考にしてみてください。


特定活動「EPA介護福祉士・候補者」
EPA(経済連携協定)は、日本がインドネシアやフィリピン、ベトナムなどと結んだ、政府間協定に基づく人材受け入れを前提として作られた在留資格です。
それぞれの国で介護関連の基礎を学んだ人材が来日し、特定の介護施設で就労しながら日本語研修や試験対策を受け、介護福祉士国家試験の合格を目指します。
在留期間は最長4年と定められており、在留期間内に合格できなかった場合は帰国しなければなりません。
在留期間中に合格できた場合は在留資格が候補者から「EPA介護福祉士」に切り替わり、引き続き日本で就労可能です。
- 合格基準点の5割以上を取得
- すべての試験科目で得点があること
上記2つの条件を満たしていれば在留資格を「特定技能」に変更して最長5年間まで就労しながら再受験できます。
在留資格を変更した後に介護福祉士に合格した場合は、EPA介護福祉士ではなく在留資格「介護」に切り替えることで日本に引き続き在留可能です。
「国籍別の特徴や強みを知りたい!」という方に向けて国籍別外国人採用ガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
介護分野で働ける在留資格の違いとは?【比較表あり】


それぞれの資格はどのような点で異なるのかを、以下5つの観点から解説します。
- 取得人数
- 取得要件
- 在留期間
- 転職
- 家族帯同の可否
取得人数
| 在留資格 | 在留者数 |
|---|---|
| 在留資格「介護」 | 9,328人 |
| 技能実習 | 14,751人 |
| 特定技能 | 31,453人 |
| 特定活動「EPA介護福祉士・候補者」 | 3,074人 |
参考:厚生労働省|令和6年度実施施策に係る政策評価の事前分析表介護福祉士国家資格が必須条件の在留資格「介護」の取得者は、2023年12月時点では9,328人です。
技能実習は開発途上国の多くの若者に門戸が開かれている制度であるため、技能実習は応募者が非常に多い傾向にあります。2024年6月末時点では14,751人の外国人が介護の技能実習生として在留資格を取得し、日本に在留しています。
特定技能は試験合格で比較的早く就労を開始できるため、技能実習からの移行なども相まって増加傾向が見られる在留資格です。
2024年2月末時点では31,453人が特定技能で在留しているデータからも、特に介護業界で働く外国人労働者は特定技能が多いことがわかります。
EPAは政府間の交渉により受け入れ枠が決められるため、受け入れ人数が4つの資格の中でもっとも少ない在留資格です。2024年6月時点では3,074人が受け入れられています。
取得要件
| 在留資格 | 主な取得要件 |
|---|---|
| 在留資格「介護」 | ・国家資格「介護福祉士」の取得 ・介護施設との雇用契約 ・日本人と同等以上の報酬 |
| 技能実習 | ・日本語スキルは1年目(入国時)はN3程度が理想的であり、N4程度が要件2年目からはN3程度が要件 ・国家資格不要 |
| 特定技能 | 介護技能評価試験合格介護日本語評価試験合格日本語能力試験N2レベル以上または日本語基礎テスト合格 |
| 特定活動「EPA介護福祉士・候補者」 | 【共通】 ・在留中の国家資格「介護福祉士」受験・合格 ・病院または介護施設での研修経験 【フィリピン・インドネシア】 介護研修経験/日本語能力試験N5以上 【ベトナム】 介護研修経験/日本語能力試験N3以上 |
参考:厚生労働省|外国人介護職員と一緒に働いてみませんか?
参考:厚生労働省|インドネシア人看護師・介護福祉士候補者 令和元年度受入れスキーム
参考:出入国在留管理庁|「特定技能外国人受け入れる際のポイント」
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士国家試験の合格が必要です。
また、日本国内の介護施設などと雇用契約を結ばなければいけません。取得要件が多くハードルは高く、実務上に必要な高い日本語力も求められる在留資格です。



技能実習は基本的に国家資格が不要で、送り出し国からの推薦や日本語の基本的なコミュニケーション力があればスタートできます。
特定技能は、以下すべての試験に合格しなければ、就労は許可されません。
- 介護技能評価試験
- 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
- 介護日本語評価試験
EPAはどの国出身でも介護研修経験が必須ですが、国ごとに求められる日本語レベルの水準は異なります。
たとえばフィリピン・インドネシアでは、カタコトで話せるような日本語能力試験N5程度以上の日本語スキルがあれば、EPAの要件を満たします。
しかし、ベトナムでは同じEPAでも日常会話レベルであるN3以上に合格しなければいけません。
どの国からの来日であってもEPAは介護関連の基礎学習が前提となり、来日後は介護福祉士国家試験の合格をゴールとしながら施設で働きます。
在留期間
| 在留資格 | 在留期間 | 更新・延長の可能性 |
|---|---|---|
| 在留資格「介護」 | 5年、3年、1年、3ヵ月のいずれか | 更新回数の制限なし、永続的な在留が可能 |
| 技能実習 | 最長5年まで | 1号から3号まで段階的に移行、5年経過後は原則帰国 |
| 特定技能 | 通算5年まで | 5年経過後は原則終了。ただし介護福祉士資格取得で在留資格「介護」へ変更可能 |
| 特定活動「EPA介護福祉士・候補者」 | 最大4年 | EPA介護福祉士候補の間は在留年数上限が4年介護福祉士試験に合格して活動内容が「EPA介護福祉士」に切り替わったあとは、在留年数の上限無しで更新可能 |
参考:厚生労働省|外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック
参考:厚生労働省|外国人介護職員を雇用できる4つの制度を比較してみましょう
在留資格「介護」の在留期間は5年・3年・1年・3ヵ月のいずれかで更新可能です。ほかの在留資格とは異なり、在留資格「介護」は更新回数や在留可能年数などの制限がありません。
技能実習は1号・2号・3号と段階を経て最長5年まで滞在可能です。5年以上延長して就労はできないため、原則として帰国する必要があります。
特定技能は最大5年間の在留が認められており、原則として5年を過ぎた後は延長できません。
ただし、在留期間中に介護福祉士を取得して要件を満たせば、在留資格を特定技能から在留資格「介護」に変更して引き続き日本に在留可能です。
EPA介護福祉士候補は最大4年の在留期間の中で、介護福祉士試験に合格しなければいけません。
在留期間中に合格できなかった場合は原則として帰国となりますが、合格すれば活動内容が「EPA介護福祉士」に切り替わり、引き続き日本で就労できます。
転職
| 在留資格 | 転職 |
|---|---|
| 在留資格「介護」 | 可能 |
| 技能実習 | 原則不可 |
| 特定技能 | 可能 ※一部条件あり |
| 特定活動「EPA介護福祉士・候補者」 | 原則不可 |
在留資格「介護」は、名前のとおり介護福祉士として就労するための在留資格のため、同一の業務内容であればほかの施設や事業所へ転職可能です。
技能実習は原則として転職が認められていません。
ただし、技能実習制度をベースに作られた2027年から導入予定の「育成就労制度」では、やむを得ない場合は職場の変更を認めるように改善される予定です。
特定技能においては、転職時にも在留資格の変更許可申請を行う必要があります。



審査に通れば転職可能ですが、審査中は転職先企業でアルバイトやパート勤務などができない点に注意してください。
EPA介護福祉士候補者においても、介護福祉士取得前の転職が原則として認められていません。対して、介護福祉士に合格した後に在留資格「介護」の変更許可申請が通れば転職可能です。
家族帯同の可否
| 在留資格 | 家族帯同 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格「介護」 | ◯ | 配偶者と子どもに「家族滞在」ビザで在留できるため、帯同可能 |
| 技能実習 | × | 研修制度のため家族帯同は不可 |
| 特定技能 | × | 単身赴任が前提のため、家族帯同は不可 |
| 特定活動「EPA介護福祉士・候補者」 | △ | 介護福祉士合格前は家族帯同が不可合格後に活動内容が「EPA介護福祉士」に切り替わったあとは家族帯同が可能 |
参考:厚生労働省|在留資格「介護」
参考:法務省|特定技能制度に関するQ&A
参考:厚生労働省|外国人介護職員を雇用できる4つの制度を比較してみましょう
在留資格「介護」は家族帯同が許可されますが、ほか3つの在留資格では原則として家族帯同が認められていません。
ただし、EPA介護福祉士候補者は、介護福祉士に合格して活動内容がEPA介護福祉士に変更されたあとは家族帯同が可能です。
介護分野で働ける外国人を雇用するまでの流れ


介護分野で働ける外国人を雇用するまでの流れを5ステップで解説します。
- 外国人労働者の受け入れ準備
- 採用活動を開始
- 雇用契約の締結
- 在留資格の取得・変更
- 就労スタート
また、「外国人雇用の手順や注意点を詳しく知りたい!」という方に向けて、外国人雇用スタートガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
1.外国人労働者の受け入れ準備
まずは、社内で外国人労働者の受け入れ準備を進めます。
以下は外国人が働きやすい環境を整えるための事前準備の一例です。
- 日本人スタッフ向けの多文化理解に関する研修を実施する
- 多言語に対応したマニュアル作成する
- 外国人専用の相談窓口を設置する
- 住居確保のサポートも行う
外国人労働者は環境が新しく変わるため、不安を抱えている場合があります。早く職場に適応できるよう受け入れ準備をしっかり行いましょう。
なお、在留資格「特定技能」の場合は、支援計画書の作成と義務的支援(就労面・生活面のサポート)の実施が必要です。
詳細は弊社が無料でお配りしている特定技能制度まるわかりガイドの資料にて解説しています。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
2.採用活動を開始
外国人労働者の受け入れ準備完了後は、採用活動をスタートします。介護分野の在留資格をもつ外国人労働者を募集するには、主に以下の方法があります。
- SNSで募集情報を投稿する
- ハローワークに求人を登録する
- 求人サイトに募集広告を掲載する
- 人材紹介会社で希望に合った人材を紹介してもらう
- 大学や専門学校のキャリアセンターに求人を掲載してもらう
応募者が集まったら、在留カードで在留資格の有無や在留期間などを確認し、面接を実施しましょう。面接では日本語能力や介護知識、人柄を総合的に踏まえ、自社にマッチする人材を見つけてください。
なお、更新手続きをせずに在留期間が過ぎていた場合、オーバーステイになります。オーバーステイの外国人労働者を雇用した場合は企業側も罰則を受ける恐れがあります。
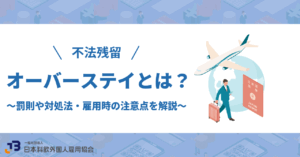
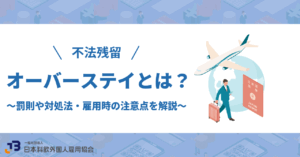
3.雇用契約の締結
自社に合う人材が見つかれば、雇用契約の締結を行いましょう。
雇用契約書に記載する主な内容は以下のとおりです。
- 業務内容
- 賃金や支払い方法
- 勤務時間
- 福利厚生
- 契約解除の取り決め
契約内容の誤認によるトラブルの発生を防ぐために雇用契約書は、外国人労働者が理解できる母国語または英語で作成してください。※技能実習・特定技能の場合は、外国人が理解できる言語での雇用契約書作成は必須対応
4.在留資格の取得・変更
外国人労働者の雇用後、在留資格の取得・変更が必要な場合があります。
具体的な取得・変更パターンは以下のとおりです。
- 技能実習・特定活動(EPA)の内定者は海外から来日するため認定申請を行う
- すでに特定活動(EPA)で活動中であり介護福祉士国家試験の合格後
- 留学生から特定技能介護分野の在留資格に変更する
- 特定技能介護分野で就労中の方で介護福祉士国家試験に合格し、在留資格「介護」に変更する
在留資格の取得・変更手続きは書類の不備や要件の不一致があると不許可になります。確実に申請許可を得るためにも、在留資格ごとの手続き方法の理解を深めておきましょう。
自社の外国人雇用の担当者が在留資格の取得や変更に不慣れな場合は、行政書士法人に依頼する選択肢もあります。
行政書士法人は在留資格の取得・変更を含めた公的手続きの専門家です。専門的な知識と豊富な経験により、許可率を向上させられます。




5.就労スタート
在留資格の許可が下りて在留カードを受け取ると、いよいよ就労開始です。



在留資格ごとに活動内容に制限があるため、規則を守りながら外国人労働者を雇用します。
また、雇用後は外国人労働者が安心して働けるよう、以下のようなサポートを実施しましょう。
- 社内研修を開催する
- 日本語学習の場を提供する
- 母国語で相談できるスタッフを配置する
- 義務的支援を行う(特定技能1号の場合)
丁寧なフォローが転職や失踪を防ぎ、安定的な雇用につながります。
「外国人の社内研修ってどんな内容がいいの?」とお困りの方に向けて、外国人の教育・研修のコツ・注意すべき落とし穴の資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、どうぞお受け取りください。
なお、特定技能1号に実施する義務的支援(就労面・生活面のサポート)は「登録支援機関」に委託する選択肢もあります。登録支援機関とは企業からの委託を受けて、外国人の就労を支援する専門家です。
義務的支援について、内容把握から実施まで自社でスムーズに進める自信がない場合、登録支援機関に委託しましょう。
どの登録支援機関に委託すればよいのか迷ったら「日本料飲外国人雇用協会」がおすすめです。
外国人向けの人材紹介会社で、介護業界の就労支援を強みとしています。登録支援機関の認定も受けているため、特定技能1号外国人の支援計画書の作成や義務的支援もサポートが可能です。
\業界平均約2倍の定着率を実現!/
介護の在留資格をもつ外国人を雇用するなら「FES行政書士法人」にご相談ください


「介護の在留資格について理解できたけど、自社で手続きをスムーズに進められるか不安…」
このようにお悩みの方は「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、外国人雇用の公的手続きを支援する行政書士法人です。在留資格の取得や変更、更新などの手続きが円滑に進むよう丁寧にサポートいたします。
外国人雇用の手続きに特化しているため、豊富な経験にもとづく的確な判断で不許可になるリスクを最小限に抑えます。
また、外国人向けの人材紹介会社で登録支援機関の認定を受けている「日本料飲外国人雇用協会」と連携しているため、人材紹介や特定技能1号の義務的支援の実施も可能です。
無料相談を受け付けていますので、外国人雇用における必要書類の準備や作成にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
在留資格「介護」に関するよくある質問


最後に、在留資格「介護」に関するよくある質問と回答を紹介します。
外国人の「介護福祉士」合格率は?
厚生労働省が公開している資料「介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」によると、近年の外国人受験者の合格率は、以下のように年々上昇傾向にあります。
- 第31回(平成30年度実施):73.7%
- 第32回(令和元年度実施):69.9%
- 第33回(令和2年度実施):71.08%
- 第34回(令和3年度実施):72.3%
- 第35回(令和4年度実施):84.3%
- 第36回(令和5年度実施):82.8%
- 第37回(令和6年度実施):78.3%
参考:厚生労働省|介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移
第37回の試験の合格率は78.3%で、直近2年と比較すると低下しました。しかし、過去7年間の合格率の推移を確認すれば、年々上昇傾向にあります。日本語学習支援や研修体制などの充実により、しっかり対策を行えば外国人でも介護福祉士の合格を狙える環境が整備されています。
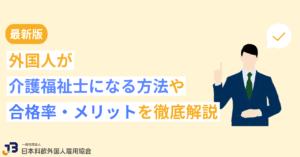
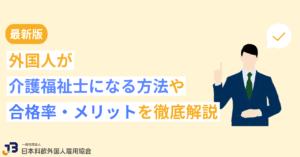
介護の在留資格から永住権を取得できますか?
在留資格「介護」で働き続けて日本での在留実績を積めば、将来的な永住権取得に有利に働きます。
一般的に永住権取得には10年間の在留が必要とされており、うち5年以上が就労目的の在留資格であれば審査対象になり得るため、在留資格「介護」での長期勤務は永住権取得を後押しする理由になります。
介護の在留資格を更新するときの方法を教えてください
在留期限が近づいたら、満了の約3ヵ月前から出入国在留管理局で更新申請を行います。
基本的には以下4つの必要書類を揃えて提出すると1〜3ヵ月ほどで審査が完了します。
- 在留期間更新許可申請書:1通
- カードに表示する証明写真:1枚
- パスポートおよび在留カード
- 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書:各1通
参考: 出入国在留管理庁|在留資格「介護」
なお、介護業界内で転職してからはじめて更新する際は、労働条件通知書や転職先企業の概要が記載された文書なども提出しなければいけません。


介護の在留資格の経過措置について教えてください
平成29年4月1日から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方は、介護福祉士国家試験に不合格であっても5年間は介護福祉士の資格を有する者として扱われます。
また、以下2つの条件のいずれかを達成すれば、5年後も継続して介護福祉士として登録可能です。
- 5年の間に介護福祉士国家試験に合格する
- 養成施設卒業年度の翌年度の4月1日から5年間継続して介護等の業務に従事する
養成施設卒業後、5年間継続して介護等の業務に従事した場合、継続して介護福祉士として登録するには届出が必要です。
この届出を行わない場合は介護福祉士登録が失効します。企業側は雇用している外国人労働者が資格を失効しないように、届出が必要なことを把握し、呼びかけや申請のサポートを行いましょう。


在留資格「介護」の種類や取得方法を知って自社にあった外国人を採用しよう


介護分野で働ける主な在留資格は、在留資格「介護」・技能実習・特定技能・特定活動「EPA介護福祉士・候補者」の4つです。それぞれ特徴や取得要件、在留期間などが異なるため、企業の人事担当者は必ず把握しておきましょう。
本記事で紹介した介護分野で働ける在留資格の特徴や違い、雇用するまでの流れを参考にして、雇用準備を進めてください。
とはいえ「介護分野における在留資格の申請手続きを自社でスムーズに進められるか不安…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、外国人雇用の就労サポートに特化した行政書士法人です。申請取次行政書士が在籍しているため、就労目的の在留資格申請の手続き代行が可能です。
無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


- FES行政書士法人は外国人就労者特化の行政書士法人
- 登録支援機関の設立支援・在留資格の変更手続き支援・外国人材育成支援など幅広く対応
- 専門分野に特化した法人ならではのサポートが充実
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿